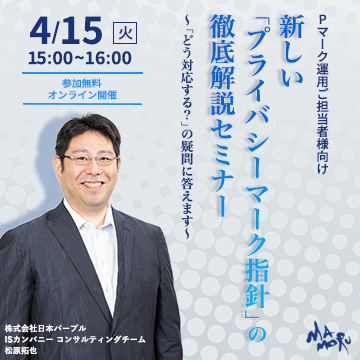契約書の電子化とは?電子契約のメリットや種類やポイントを解説

契約書は紙媒体が一般的ですが、近年では電子化されるケースが増えています。電子契約にすることで、契約書の作成や送信、合意まで電子化することができます。リモートワークの際にも重宝されるため、導入を検討している会社も多いのではないでしょうか。この記事では、電子契約のメリットやデメリット、種類やポイントなどを中心に解説します。
電子契約とは

電子契約は、契約書を電子化して電子署名を行うことで締結する契約方法です。
書面との違いや、法的有効性があるのか気になる方も多いと思います。以下で、書面の契約書との違いや、電子契約書の法的有効性について解説します。
書面の契約書との違い
電子化することで、契約書の作成、送信、合意の全てをパソコンやタブレットなどで行えることが、書面の契約書との大きな違いです。
送付はメールやシステムを経由して行われ、保管はサーバーなどで行われます。また、書面と違い印紙は不要です。
押印に関しては、書面では印鑑か印影が必要ですが、電子契約では電子署名または電子サインが用いられます。また、改ざん防止の観点から書面では割印や契印を押しますが、電子契約ではタイムスタンプを用いることで法的証拠力を担保しています。
電子契約書の法的有効性
電子契約書には書面の契約書と同様に、法的有効性があります。
電子署名がされている電子文書は、押印した書面契約と同等の法的証拠力を有することが認められており、電子署名法第3条に明記されています。電子署名は、本人だけができるものに限られています。
電子契約に関する法律は、電子署名法の他にも、「電子帳簿保存法」「印紙税法」「e-Tax法」などがあります。
電子化できない契約書もある
契約書は電子化されることが多い傾向にありますが、中には電子化できない契約書があることに注意が必要です。
現時点で電子化できない契約書は、「事業用定期借地契約」「任意後見契約書」「企業担保権の設定又は変更を目的とする契約」「農地の賃貸借契約」の4つです。
電子化できない契約書の他に、電子化する際に相手方の承諾が必要なケースもあります。
電子署名・タイムスタンプについて
電子署名は、誰が何を作成したかを証明するものです。
電子署名には、「電子サイン」と「身元確認済み高度電子署名」があります。電子サインは、メール認証によって本人であることを担保するシステムです。身元確認済み高度電子署名は、認証局の審査を経て発行した電子証明書により、本人であることを担保するシステムです。
電子契約書の種類
電子契約書は、主に4種類あります。
紙の契約書をスキャンすることによる電子契約書、PDFに電子署名することによる電子契約書、電子契約システムで契約することによる電子契約書、そして契約書管理システムで管理することによる電子契約書があります。
同じ電子契約書でも仕組みが異なるので、一部を電子化したいのか、全体を電子化したいのかによって方法が異なります。
電子契約にするメリット

電子契約にするメリットは、以下の5つです。
- ・業務効率化
- ・保管スペースが不要
- ・コストの削減
- ・セキュリティ面の強化
- ・更新時期の管理
各メリットについて順番に詳しく解説していきます。
業務効率化
電子化することで業務の効率化を図ることができるのは、大きなメリットです。
紙の契約書であれば探すのに時間がかかり、保管場所が不明確だった場合は、さらに時間がかかります。
電子化してファイル名に日付や社名を入れておけば、検索することですぐに見つけることができます。探す時間を大幅に省くことができるという点で、業務効率化への貢献度は大きいと言えるでしょう。
保管スペースが不要
保管スペースが不要になるのも、電子化することのメリットです。
紙の契約書であれば、書類が増えると保管スペースが徐々に減り、場所の確保が課題となります。
電子化することで、物理的な保管スペースが不要になるので、空いた場所を他の用途に有効活用することも可能です。
コストの削減
紙の契約書の場合、紙代や印刷代、郵送費など様々なコストがかかります。
電子化することで、紙の契約書の時に必要だったコストを削減することができます。また、紙の契約書で必要となる印紙も、電子契約では不要になります。
セキュリティ面の強化
電子化すると、セキュリティ面の強化をすることも可能です。
紙の契約書は、キャビネットなどで保管することでセキュリティ対策を行いますが、契約書一つ一つに対してアクセス制限をかけることは難しいです。
電子化すればアクセス制限をかけることができるので、必要な人だけが閲覧可能になり、情報の漏洩を防ぐことができます。
更新時期の管理
契約書を電子化することで、契約の更新時期を管理することができます。
具体的には、更新時期が近づいたら通知で知らせる、自動更新、破棄などがあります。更新手続きの負担を減らすことで、スムーズな取引につながります。
電子契約にする際の注意点

電子契約にする際は、以下の点に注意する必要があります。
- ・「電子帳簿保存法」に準拠する必要がある
- ・導入費用と月額費用がかかる
- ・電子契約に抵抗のある取引先もある
それぞれの注意点について順番に詳しく解説していきます。
「電子帳簿保存法」に準拠する必要がある
電子帳簿保存法とは、個人事業主を含めた事業者が対象となる法律です。
電子化した契約書を保存する場合は、「電子帳簿保存法」に準拠している必要があります。
準拠していない場合は、準拠するための対応が必要になります。
導入費用と月額費用がかかる
契約書の電子化は、方法によっては導入費用と月額費用がかかります。
スキャナが既にある場合や、PDF化の場合は導入費用はかかりません。ただし、電子帳簿保存法のルールによりタイムスタンプが必要になるので、そのための費用はかかります。
システムを利用する場合は、初期費用と月額費用がかかります。費用対効果があるかどうかは、社内で事前に検討したほうが良いでしょう。
電子契約に抵抗のある取引先もある
電子契約を導入する会社は増加傾向にありますが、電子契約に抵抗のある取引先も少なくないことに注意しましょう。
取引先から「書面での契約を行いたい」と提案されると、拒否するのは困難だと思います。電子契約がメインになっている会社でも、様々なケースを想定して、書面の契約書を用意できるように準備しておくのが無難です。
電子契約サービスを選ぶ際のポイント

電子契約サービスを選ぶ際は、以下のポイントに注目することが重要です。
- ・取引先が導入しやすい
- ・書面契約にも対応している
- ・電子帳簿保存法に対応している
- ・セキュリティ機能が充実している
それぞれのポイントについて、以下で詳しく見ていきましょう。
取引先が導入しやすい
取引先が導入しやすい環境を作れば、取引先は電子契約を行いやすくなります。
利用料が無料で、分かりやすいマニュアルや支援体制が整っているサービスを選ぶのがおすすめです。
書面契約にも対応している
状況に応じて、書面契約が必要になることも考えられます。
電子契約サービスの中でも、紙の契約書にも対応しているサービスを利用すれば、電子契約と書面契約を一括で管理できるので便利です。
電子帳簿保存法に対応している
電子データを保管するための要件が、電子帳簿保存法に定められています。
保管するためには要件を満たしていなければならず、満たしていない場合は電子帳簿保存法に対応した保存を行う必要があります。
セキュリティ機能が充実している
電子契約書は、サイバー攻撃や情報漏洩などの被害に遭うリスクがあります。
セキュリティ機能が充実している電子契約サービスを選べば、安全に契約書を保管することができます。
電子契約サービスの導入する際のポイント

電子契約サービスを導入する際は、以下のポイントを意識しておくことが重要です。
- ・導入目的を明確にする
- ・電子契約サービスを比較検討する
それぞれのポイントについて、以下で確認しましょう。
導入目的を明確にする
電子契約サービスを導入するにあたり、導入目的を明確にすることが重要です。
なぜ導入する必要があるのか、導入することでどのようなメリットがあるのか、事前に社内で共有しておくとスムーズな導入につながります。
電子契約サービスを比較検討する
電子契約サービスには様々な種類があるので、複数のサービスを比較検討することが大切です。
利用料金や利便性。自社のニーズに合っているかなど、複数の観点から様々なサービスを比較することをおすすめします。
まとめ

契約書の電子化は増加傾向にあり、これから更に電子化が進むと考えられます。電子契約にすることで保管スペースを省いたり、コストの削減につながるなど、様々なメリットがあります。電子契約書の導入を検討している場合は、この記事に書かれていることを踏まえて、自社にあったサービスを導入するための参考にしてみてはいかがでしょうか。
契約書を電子化して保管したいとお考えの際は、「ConPass(コンパス)」のご利用をご検討ください。
「ConPass」は電子・紙共にクラウド管理でき、契約期限を通知したり、押印・郵送・受取、スキャニングから原本の保管、修正履歴の管理など、契約書管理業務のすべてを一元管理できるサービスです。