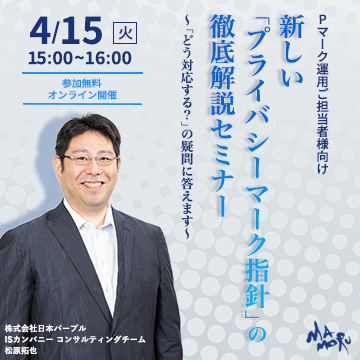書類の保管期間一覧!保管が必要な理由や保存方法・処分方法を解説
仕事で扱う様々な書類をそのままにしておくと、増え続けてしまい、置く場所に困ってしまいます。書類は保管期間を過ぎると処分することができるので、保管期間を知っておくことは重要です。保管期間は法律で決まっているタイプと、そうでないタイプに分かれています。この記事では、書類の保管が必要な理由と保管期間、さらに保管方法や処分方法について解説します。
書類の保存が必要な理由

書類の保存期間は、法律で保存期間が定められているものと、それ以外の2種類に分けられます。
法律で保存期間が定められている書類は、法定保存文書と呼ばれます。法人税法や会社法、雇用保険法など様々な法律を根拠として、保存期間が定められています。
保存期間中は書類を保存しておかないと、罰則が科される、社会的信用を失う、といったリスクがあるので注意が必要です。
法定保存文書の保存期間一覧
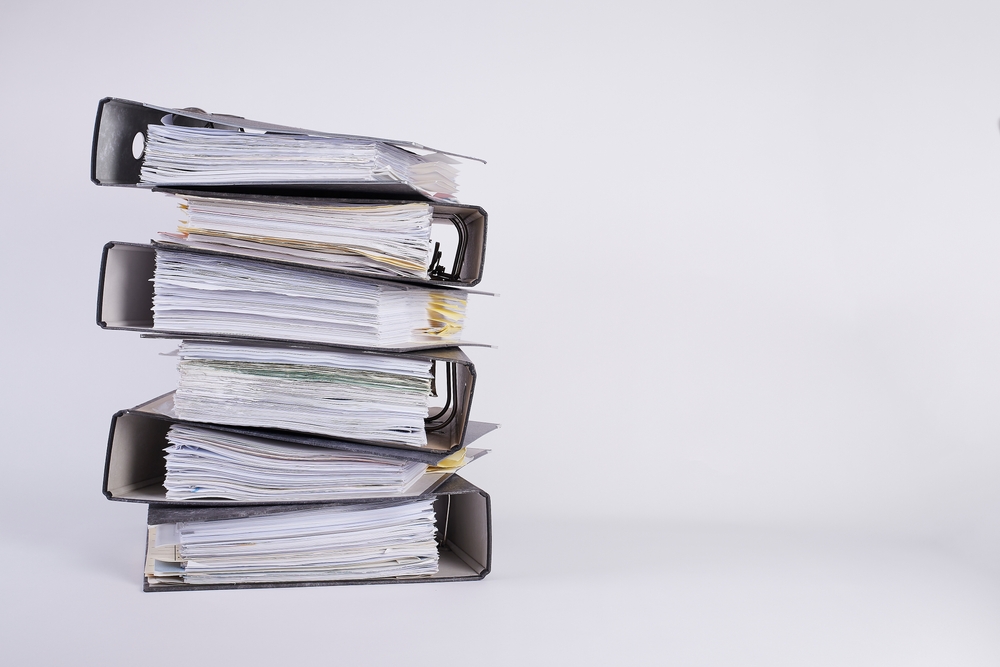
法定保存文書の保存期間は、1年から40年、書類によっては永久保存する場合もあります。
保存期間の長い書類から順に紹介しますので、以下で確認していきましょう。
永久保存の書類
法律上の保存期間はありませんが、書類の性質上、永久保存が必要とされている書類は以下の通りです。
総務・庶務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 定款 | 保存期間が定められていないため、特になし | 法律で定められた保存期間は無いが、文書の性質上、永久保存が必要と考えられている。 |
| 株主名簿、社債原簿、端株原簿、新株予約権原簿、株券喪失登録簿 | ||
| 登記や訴訟関係の書類 | ||
| 官公庁に提出する文書、官公署から受領した許可書、認可書、通達などに関する書類 社規、社則、および通達文書 | ||
| 効力の永続する契約に関する文書 | ||
| 知的所有権に関する書類 | ||
| 重要な権利や財産の得喪等に関する文書 | ||
| 社報、社内報、重要刊行物 | ||
| 製品の開発や設計に関する重要文書 |
人事・労務に関する文書
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 労働協約にあたる書類 (確認書・覚書) | 保存期間が定められていないため、特になし | 法律で定められた保存期間は無いが、文書の性質上、永久保存が必要と考えられている。 |
40年保存する書類
保存期間が40年となっている書類は、以下の通りです。
人事・労務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 石綿健康診断個人票 | 業務に従事しなくなった日 | 石綿障害予防規則 |
30年保存する書類
保存期限が30年となっている書類は、以下の通りです。
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| クロム酸等の空気中における濃度の定期測定記 | 作成日 | 特定化学物質障害予防規則36条 |
| 特別管理物質についての作業の記録 | 当該事業場において常時当該作業に従事することとなった日 | 特定化学物質障害予防規則38条の4 |
| 放射線業務従事者の線量の測定結果記録 ※当該記録を5年保存した後、厚生労働大臣が指定する期間に引き渡すときはこの限りでない。 | 作成日 | 電離放射線障害防止規則9条 |
| 電離放射線健康診断個人票 ※当該記録を5年保存した後、厚生労働大臣が指定する期間に引き渡すときはこの限りでない。 | 作成日 | 電離放射線障害防止規則57条 |
| 特別管理物質を取り扱う業務に携わる労働者の特定化学物質健康診断個人票 | 作成日 | 特定化学物質障害予防規則40条 |
10年保存する書類
保存期間が10年となっている書類は、以下の通りです。
総務・庶務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 株主総会議事録 (本店据え置き分の場合。支店据え置き分の場合は謄本を5年保存) | 株主総会の日 | 会社法318条 |
| 取締役会議事録 | 取締役会の日 | 会社法371条 |
| 監査役会議事録 | 監査役会の日 | 会社法394条 |
| 委員会議事録 (監査委員会、指名委員会、報酬委員会) | 委員会の日 | 会社法413条 |
| 重要会議の記録 | 記録作成の日 | 法律上の定めはないが、保管が望ましい。 |
| 満期または解約となった契約書 | 満期または解約の日 | 法律上の定めはないが、保管が望ましい |
| 製品の製造、加工、出荷、販売の記録 ※民法724条では、20年が期限 | 製品の引渡し日 | 製造物責任法5条、6条 |
経理・税務に関する文書
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 計算書類および付属明細書 (貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) | 作成した日 | 会社法435条 |
| 会計帳簿および事業に関する重要書類 (総勘定元帳、各種補助簿、株主申込簿、株式台帳、株主名義書換簿、配当簿、印鑑簿など) | 帳簿閉鎖の時 | 会社法432条 |
7年保存する書類
保存期間が7年となっている書類は、以下の通りです。
労働安全衛生に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 粉じん濃度の測定記録、測定結果の評価記録 | 作成日 | 障害防止規則26条、26条の2 |
| じん肺健康診断記録、じん肺健康診断に係るエックス線写真 | 作成日 | じん肺法17条 |
経理・税務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 取引に関する帳簿 (仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 | 法人税法施行規則59条、67条 |
| 決算に関して作成された書類 (上に挙げた、会社法で10年保存が義務付けられている書類以外) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 | 法人税法施行規則59条、67条 |
| 現金の収受、払出し、預貯金の預け入れ・引き出しに際して作成された取引証憑 (領収書、預金通帳、借用書、小切手、手形控、振込通知書など) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 | 法人税法施行規則59条、67条 |
| 有価証券の取引に際して作成された証憑書類 (有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書など) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 | 法人税法施行規則59条、67条 |
| 取引証憑書類 (請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 | 法人税法施行規則59条、67条 |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書 | 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日 | 所得税法施行規則76条の3、77条、77条の4、措規18条の23 |
| 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日 | 措規18条の23 |
| 源泉徴収簿 (あるいは源泉徴収簿を兼ねた貸金台帳) | 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日 | 国税通則法70条~73条 |
| 課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書等 (6年目以降は、帳簿または請求書のいずれかを保存) | 確定申告期限の翌日 | 消費税法30条、消費税法施行令50条、消費税法施行規則15条の3 |
| 資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿 | 閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月の経過した日 | 消費税法58条、消費税法施行令71条 |
5年保存する書類
保存期間が5年となっている書類は、以下の通りです。
総務・庶務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 事業報告(本店備置き分。支店備置き分は、その謄本を3年保存) | 事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 | 会社法442条 |
| 有価証券届出書・有価証券報告書およびその添付書類、訂正届出(報告)書の写し | 提出した日 | 金融取引法25条 |
| 産業廃棄物管理表(マニフェスト)の写し | 提出した日 | 産業物の処理及び清掃に関する法律施行規則8条の26 |
| 産業廃棄物処理の委託契約書 | 契約の終了の日 | 産業物の処理及び清掃に関する法律施行規則8条の4の3 |
経理・税務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 貸金台帳(源泉徴収簿を兼ねていないもの) | 最後に書き入れた日 | 労働基準法109条、労働基準法施行規則56条 |
| 監査報告(本店備置き。支店備置き分はその謄本を3年保存) ※監査役設置会社等の場合 | 株主総会の1週間(取締役会設置会社は2週間)前の日 | 会社法442条 |
| 会計監査報告(本店備置き分。支店備置き分はその謄本を3年保存) ※会計監査人設置会社の場合 | 株主総会の1週間(取締役会設置会社は2週間)前の日 | 会社法442条 |
| 会計参与が備え置くべき計算書類、附属明細書、会計参与報告 (会計参与設置会社の場合。会計参与が定めた場所に備置き) | 株主総会の1週間(取締役会設置会社は2週間)前の日 | 会社法378条 |
| 金融機関等が保存する非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度変更申告書、 非課税貯蓄異動申告書、非課税貯蓄勤務先異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書などの写し | 申告書、退職等に関する通知書等の提出があった年の翌年 | 所得税法施行令48条 所得税法施行規則13条 租税特別措置法施行令2条の21租税特別措置法施行規則3条の6 |
| 金融機関等が保存する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書などの写し | 申告書、退職等に関する通知書等の提出があった年の翌年 | 所得税法施行令48条 所得税法施行規則13条 租税特別措置法施行令2条の21 租税特別措置法施行規則3条の6 |
| 金融機関等が保存する退職等に関する通知書 | 申告書、退職等に関する通知書等の提出があった年の翌年 | 所得税法施行令48条 所得税法施行規則13条 租税特別措置法施行令2条の21 租税特別措置法施行規則3条の6 |
人事・労務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 従業員の身元保証書 | 作成日 | 身元の保証二関スル法律1条、2条 |
| 誓約書などの書類 | 作成日 | ― |
| 資金その他労働関係の重要書類 (労働時間を管記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など) | 賃金支払期日 | 労働基準法109条、労働基準法施行規則56条 |
| 労働者名簿 | 完結の日 | 労働基準法109条、労働基準法施行規則56条 |
| 雇入れ・解雇・退職に関する書類 | 完結の日 | 労働基準法109条、労働基準法施行規則56条 |
| 災害補償に関する書類 | 災害補償の終わった日 | 労働基準法109条、労働基準法施行規則56条 |
| 一般健康診断個人票 | 作成日 | 労働安全衛生規則51条 |
| 有機溶剤等健康診断個人票 | 作成日 | 有機溶剤中毒予防規則30条 |
| 鉛健康診断個人票 | 作成日 | 鉛中毒予防規則54条 |
| 四アルキル船健康診断個人票 | 作成日 | 四アルキル鉛中毒予防規則23条 |
| 特定化学物質健康診断個人票 | 作成日 | 特定化学物質障害予防規則40条 |
| 高気圧業務健康診断個人票 | 作成日 | 高気圧作業安全衛生規則39条 |
| 高圧室内業務の減圧状況の記録 | 作成日 | 高気圧作業安全衛生規則20条 |
| 線量当量率の測定の記録 | 作成日 | 電離放射線障害防止規則54条 |
| 放射性物質の濃度測定の記録 | 作成日 | 電離放射線障害防止規則55条 |
| 安全委員会議事録 | 作成日 | 労働安全衛生規則23条 |
| 衛生委員会議事録 | 作成日 | 労働安全衛生規則23条 |
| 救護に関する訓練の記録 | 作成日 | 労働安全衛生規則24条の4 |
| 危機・有害業務に従事するときの安全衛生のためのときの安全衛生のための特別教育の記録 | 作成日 | 労働安全衛生規則38条 |
4年保存する書類
保存期間が4年となっている書類は、以下の通りです。
人事・労務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 雇用保険の被保険者に関する書類 (雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、同転勤届受理通知書、同資格喪失確認通知書{離職証明書の事業主控}など) | 完結の日 | 雇用保険法施行規則143条 |
3年保存する書類
保存期間が3年となっている書類は、以下の通りです。
総務・庶務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 四半期報告書、半期報告書およびその訂正報告書の写し | 提出した日 | 金融商品取引法25条 |
人事・労務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 企画業務型裁量労働制についての労使委員会の決議事項の記録 | 決議の有効期間中およびその満了日 | 労働基準法施行規則24条の2の3 |
| 労使委員会議事録 | 開催日 | 労働基準法施行規則24条の2の3 |
| 労災保険に関する書類 | 完結の日 | 労働者災害補償保険法施行規則51条 |
| 労働保険の徴収・納付等の関係書類 | 完結の日 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則72条 |
| 家内労働者帳簿 | 最後の記入をした日 | 家内労働法施行規則24条 |
| 派遣先管理台帳 | 派遣終了日 | 労働者派遣法37条 |
| 派遣元管理台帳 | 派遣終了日 | 労働者派遣法42条 |
| 身体障害者等であることを明らかにすることができる書類 (診断書など) | 最後の記入をした日 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則43条、45条 |
2年保存する書類
保存期間が2年となっている書類は、以下の通りです。
人事・労務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 雇用保険に関する書類 (雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届など) | 完結の日 | 雇用保険法施行規則143条 |
| 健康保険・厚生年金保険に関する書類 (被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書など) | 完結の日 | 健康保険法施行規則34条、厚生年金施行規則28条 |
1年保存する書類
保存期間が1年となっている書類は、以下の通りです。
総務・庶務に関する書類
| 文書名 | 起算日 | 根拠となる法律 |
| 臨時報告書、自己株券買付状況報告書およびそれぞれの改正報告書の写し | 提出した日 | 金融商品取引法25条 |
法定保存文書以外の保存期間

法定保存文書以外の書類は、会社ごとに保存期間を決めることになります。
全社で保存期間を統一するのが理想的ですが、難しい場合も考えられます。最初は部門ごとに決めて、徐々に全社で一律の保存期間にシフトできるように調整すると良いでしょう。
会社にとって重要な書類であれば、破棄せずに保存しておくという方法もあります。
書類を保存が必要・不要で分類する
法定保存文書以外の書類の保存期間を定めるためには、保存が必要な書類と不要な書類を分類する所から始まります。
以下で、ケースごとに書類の扱い方について解説します。
保存が必要な書類
会社にとって重要かどうかが、保存するかどうかの判断基準となります。
重要であれば、保存が必要な書類に分類しましょう。原本が別にある場合、あるいは電子データがある場合は、保存する必要はありません。
保存の判断に迷う書類
不要な書類は処分で問題ありませんが、保存の必要があるかどうか判断に迷うケースも珍しくありません。
判断に迷う書類は、期限を設けた上で判断を保留することをおすすめします。期限までに使わなかった書類は「保存が不要な書類」として扱うことで、スムーズに処分することができます。
保存が必要な書類の確認
「保存が必要」に分類した書類を、一定期間をかけて集めましょう。
数ヶ月~1年ほど時間をかけて、ある程度の量を集めれば、保存が必要なのかどうか判断しやすくなります。最終的に保存が必要無いと判断した場合は、処分しても問題ないと言えるでしょう。
保存期間の設定
保存期間の設定の仕方は、会社の状況に応じて変わります。
個人事業主の場合は、自分で保存期間を決めることになります。会社によっては、組織内で意思決定の場を設けて、保存期間を決めるケースもあります。
具体的に決めることが難しい場合は、短期・中期・長期など大まかに分類することをおすすめします。
また、法的な拘束力がないため、期限の変更や保存の中止を行っても大丈夫です。
書類の保管方法

書類の保管方法は、紙か電子データかのどちらかになります。
それぞれの方法について、以下で解説します。
紙での保管
税法で保管が義務付けられている帳簿や書類は、紙での保管が原則とされていました。
しかし、2022年1月に電子帳簿保存法が改正されたことによって、特定のデータは紙での保存が禁止されることになりました。
ペーパーレス化は今後も進むとされており、書類は電子データでの保管がメインになることが予想されます。
電子データでの保管
電子帳簿保存法の改正により、紙から電子データへの切り替えを本格的に検討する会社は増加傾向にあります。
電子データで保存するメリットと、電子帳簿保存法の内容について、以下で解説します。
電子データで保存するメリット
電子データで保存するメリットは、紙で保存する際に発生するコストを削減できる、という点にあります。
紙の場合は保存するのに手間と時間がかかりますし、紙やインクの資源を消費します。また、保存するためのスペースが必要なので、書類が増えると保存場所の確保が課題になります。
電子データであれば、上記のコストを全て削減することが可能です。
電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法は、1998年に施行されました。
国税関係の帳簿や書類について、電子データでの保存を認めています。
2022年1月に改正され、電子取引データの保存については大幅な改正がされました。電子帳簿と画像データに関しては紙と電子データのどちらでも良いですが、電子取引に関しては、データでの保存が義務付けられました。
書類の電子データでの保存方法

書類の電子データでの保存方法には、以下の方法があります。
- ・記録メディアでの保存
- ・文書管理システムでの保存
それぞれの方法について、以下で解説します。
記録メディアでの保存
記録メディアは、電子データを保存しておくための媒体です。
CDやDVDなどの光ディスク、SDカードやUSBなどのフラッシュメモリなどが代表的です。他にも、HDDなどのハードディスクがあります。
文書管理システムでの保存
社内の全ての電子データを、一括管理するシステムです。
オンプレミス型と、クラウドストレージ型に分かれています。オンプレミス型は自社にサーバーを設置し、情報システムを構築するタイプです。クラウドストレージ型は、インターネット上に構築されたシステムを利用するタイプです。
まとめ

書類の保存期間は、法律で定められている場合と、会社ごとに設定する場合があります。保存期間を把握することは、処分のタイミングを正しく理解することにつながるので、重要なポイントです。書類の保存は、社内での保存以外にも、外部委託のサービスを利用するという選択肢もあります。
書類保管サービス「SHOKO」は、お預かりした機密書類を、専用保管庫で安全に保管します。外部委託のサービスを考えている方は、ぜひ「SHOKO」をご利用ください。