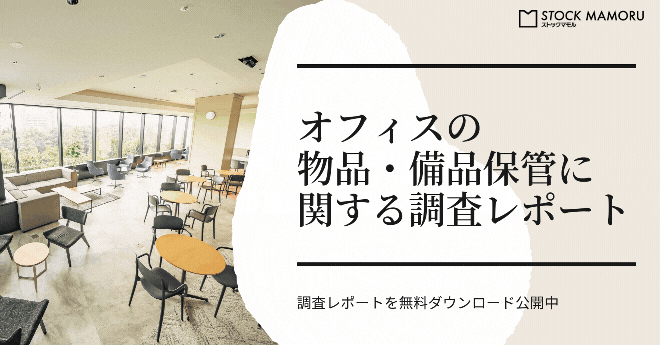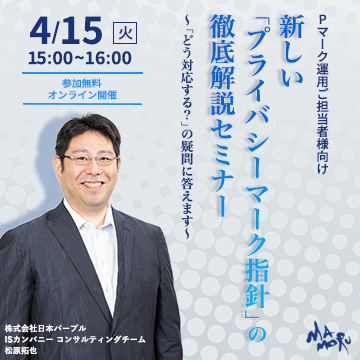物品管理とは?目的・在庫管理との違いや管理方法・注意点などを解説

企業において、備品や商品の管理は欠かせない業務のひとつです。しかし、「物品管理」と「在庫管理」の違いを正確に理解できていますか?物品管理は、単にモノを保管・整理するだけでなく、適切な運用によってコスト削減や業務効率化にもつながるものです。
この記事では、物品管理の基本から、その目的、在庫管理との違い、具体的な管理方法、注意点まで詳しく解説します。
会社での物品管理方法でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
物品管理とは
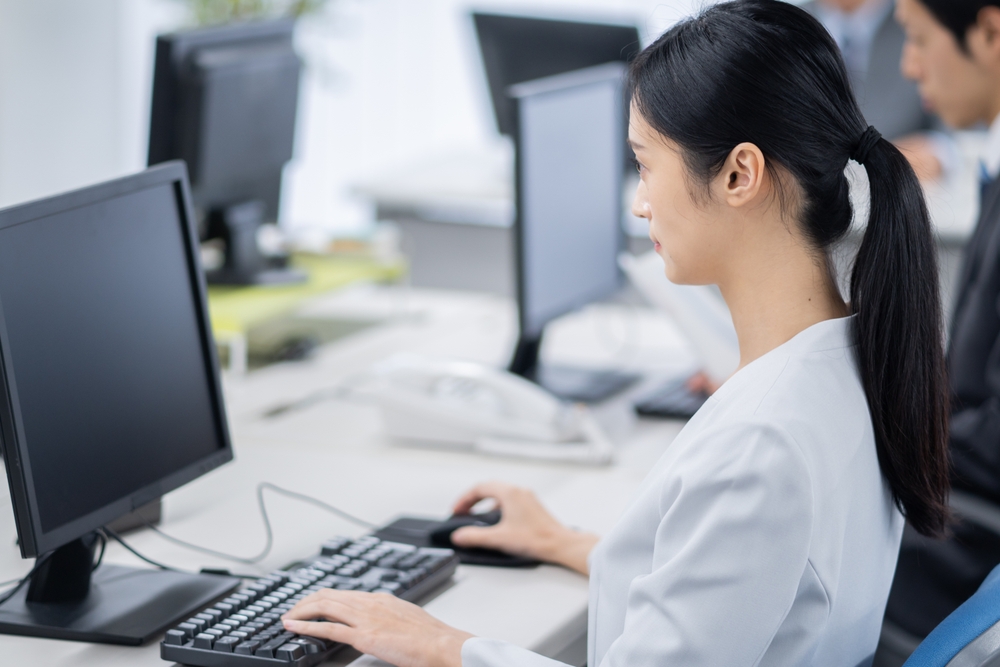
物品管理とは、企業が所有する備品や消耗品、機材などを適切に管理し、効率的に運用するための業務です。オフィスで使用する文房具やIT機器、製造業の工具や設備など、あらゆる物品が対象になります。適切な管理を行うことで、紛失や無駄な購入を防ぎ、業務の効率化やコスト削減につなげることができます。
物品管理の目的
物品管理にはさまざまな目的がありますが、主に以下の4つが重要視されています。
- ・業務の効率化
- ・セキュリティの強化
- ・コスト削減
- ・資産管理
それぞれ順番に解説していきます。
1.業務の効率化
適切な物品管理を行うことで、従業員が必要な物品をスムーズに取り扱えるようになり、無駄な時間や手間を削減できます。具体的には以下のような例が挙げられます。
必要な物品をすぐに見つけられる環境の整備
オフィスの備品や工具、機材が適切に管理されていないと、従業員が必要なものを探すのに時間を浪費してしまいます。例えば、プリンターのトナーがどこにあるのかわからず、何人もの社員が探し回る状況が発生すると、その間の業務は停滞します。適切な物品管理を行うことで、物品の保管場所を明確にし、誰でもすぐに取り出せる環境を整えることが可能になります。
物品の貸出・返却管理の最適化
企業では、社用パソコンやプロジェクター、測定機器などを共有して使用するケースが多くあります。貸出・返却の管理が不十分だと、「誰が使用中なのか分からない」「返却が遅れていて次に使えない」といった問題が発生します。こういった場合は物品管理表を作成して貸出履歴を記録することで、スムーズな利用が可能になり、業務の停滞を防ぐことができます。
物品の適正在庫を保つことで業務の中断を防ぐ
オフィスの消耗品(コピー用紙やボールペンなど)や、製造現場で使用する工具・部品が不足すると、業務が一時的に止まってしまうことがあります。しかし、過剰に在庫を抱えすぎると、スペースを圧迫し、管理コストがかかります。適切な物品管理を行い、必要な物品を必要な量だけ確保することで、無駄なスペースやコストを削減しつつ、業務の継続性を確保できます。
メンテナンス管理による業務トラブルの防止
機材や設備の適切な管理を行うことで、故障や不具合による業務トラブルを防ぐことができます。例えば、社用車のメンテナンススケジュールを管理し、定期的な点検を行うことで、急な故障による業務の遅れを回避できます。同様に、製造業では生産機械のメンテナンスを適切に管理することで、予期せぬダウンタイムを防ぐことができます。
2.セキュリティの強化
物品管理を徹底することで、企業の資産を守り、安全な業務環境を維持することができます。セキュリティの強化には、情報セキュリティと物理的な盗難防止の両面が含まれます。
情報セキュリティの強化
企業のノートパソコンや外部記憶媒体、スマートフォンなどのIT機器には、重要なデータが保存されていることが多く、紛失や盗難による情報漏えいのリスクがあります。適切な物品管理を行い、機器の貸出・返却の記録を残すことで、不正利用を防ぎ、万が一の際の追跡も可能になります。また、セキュリティ対策として、アクセス制限やデータの暗号化を施すことも有効です。
物理的な盗難防止
オフィスや工場などで使用する備品や機材の管理がずさんだと、盗難のリスクが高まります。特に、高価な機器や小型で持ち運びやすい物品は盗難されやすいため、厳重な管理が必要です。例えば、貴重品を施錠可能なキャビネットに保管したり、社外への持ち出しを厳しく管理したりすることで、盗難のリスクを軽減できます。また、監視カメラの設置や、物品に管理番号を付けるなどの対策も効果的です。
3.コスト削減
適切な物品管理を行うことで、無駄なコストの発生を抑え、企業全体の経費削減につなげることができます。具体的には、以下のような点でコスト削減が可能になります。
重複購入の防止
物品の在庫状況が適切に管理されていないと、必要がないのに同じ物品を購入してしまうことがあります。例えば、オフィスで使用する文房具や消耗品の在庫を把握していなかったために、不必要に大量のボールペンやコピー用紙を発注してしまうケースが発生します。物品管理を徹底することで、今ある備品を正確に把握し、不必要な購入を防ぐことができます。
適切なメンテナンスによる長期的なコスト削減
設備や機材の管理を怠ると、故障や劣化が早まり、頻繁に修理や買い替えが必要になります。適切な点検・メンテナンスを行うことで、突発的な修理費用の発生を防ぐ上、物品の寿命を延ばし、結果的にコスト削減につながります。
適正在庫管理による保管コストの削減
物品を過剰に抱えていると、保管スペースが圧迫され、倉庫費用や管理コストが増加します。特に、オフィスのスペースに限りがある場合、無駄な在庫のために必要な作業スペースを失うこともあります。
適切な物品管理を行うことで、必要最低限の在庫を維持し、無駄なスペースとコストの削減が可能になります。
4.資産管理
企業の資産を正確に把握し適切に管理することは、財務の透明性を高め、経営の安定化を図ることができます。
例えば、オフィス内にあるパソコンやデスク、機械設備などの固定資産を正しく管理すれば、企業全体の資産価値が明確になり、予算計画を適切に立てることができます。
また、高額な設備や機材は減価償却の対象となるため、より適切に管理しなければなりません。例えば、購入した機材の使用年数や費用を正確に記録することで、会計処理の精度を向上させ、税務申告の際のトラブルを回避できます。
物品管理と在庫管理の違いは?

物品管理と在庫管理は混同されがちですが、それぞれ管理の目的や対象が異なります。
それぞれどういったものが対象となるか順番に解説していきます。
物品管理の管理対象
物品管理の対象となるのは、企業が所有し、業務で使用する備品や機材、設備などです。これにはパソコン、デスク、プリンター、社用車などの固定資産も含まれます。
基本的に「社内で使用するもの」が中心となるため、商品在庫のように出入りが発生するものではなく、長期的に利用するものが前提となります。
在庫管理の管理対象
在庫管理の対象となるのは、販売目的の商品や生産に必要な原材料、消耗品などです。小売業や製造業では在庫の過不足を防ぎ、適切なタイミングで補充を行うことが重要となります。在庫は流動的なものであり、仕入れや販売状況によって日々変動する点が物品管理との大きな違いです。
物品管理の基本的な手順

物品管理を適切に行うためには、明確な手順を確立し、統一されたルールのもとで運用することが重要です。
以下の基本的なステップを踏むことで、効率的な管理を実現できます。
- 1.物品の状態の把握
- 2.物品保管のルール決め
- 3.物品管理台帳の作成
- 4.物品の分類・ラベルの作成/貼り付け
- 5.管理マニュアルの作成・周知
順序に沿ってそれぞれ解説していきます。
物品の状態の把握
まず、管理対象となる物品の種類、数量、状態を正確に把握することが必要です。これには、現在どのような物品がどこにあるのか、使用頻度や劣化のタイミングの把握、必要・不要の判断を含めて整理することが求められます。
特に老朽化しているものや、長期間使用されていない物品については、修理・更新・処分の検討が必要です。
物品保管のルール決め
物品の紛失や管理の混乱を防ぐために、適切な保管ルールを策定します。例えば、「使用後は必ず元の場所に戻す」「特定の担当者が管理を行う」「重要な機器は施錠可能な場所に保管する」といった明確なルールを定めることで、管理の徹底を図ることができます。
物品管理台帳の作成
物品の情報を一元管理するために、管理台帳を作成します。台帳には、「物品名」「管理番号」「購入日」「使用者」「保管場所」「状態」などの情報を記載し、必要に応じて更新します。エクセルや専用の管理システムなどを活用すると、検索や更新が容易になり、管理の精度が向上します。
物品の分類・ラベルの作成/貼り付け
物品を適切に管理するためには、カテゴリーごとに分類し、識別しやすいようにラベルを貼ることが有効です。
例えば、備品、機器、消耗品などに分類し、管理番号やバーコードを付与することで、物品の追跡や管理がスムーズになります。また、視認性の高いラベルを貼ることで、誤使用や紛失を防ぐ効果もあります。
管理マニュアルの作成・周知
関係者全員が適切に運用できるよう、ルールを明文化した管理マニュアルを作成します。マニュアルには、物品の登録・更新・廃棄の手順、貸出・返却ルール、定期点検の方法などを明記し、社内にしっかりと周知することが重要です。また、従業員の異動や新入社員が入る際にも、スムーズに引き継ぎができるよう、分かりやすい形でまとめておくことが推奨されます。
物品管理の注意点

物品管理をしっかりと行うためには、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。
管理方法が適切でないと、運用が複雑になり、かえって手間が増えてしまうこともあります。
現状の把握をしてから始める
物品管理を始める前に、まず現状の把握を行うことが重要です。現在どのような物品があるのか、どのように管理されているのかを確認し、課題を洗い出した上で最適な管理方法を検討・導入することで、スムーズな運用が可能になります。場当たり的に管理ルールを決めると、実運用が難しく、ルールを頻繁に改定する必要が出てくるなど、不要な手間が発生することがあるため、現状分析を怠らないようにしましょう。
運用フローが煩雑にならないようにする
管理のルールを細かく設定しすぎると、運用が複雑になり、現場の負担が増えてしまいます。例えば、物品の貸出・返却時に必要以上に細かい手続きを求めると、従業員が手間を感じ、管理ルールが形骸化してしまうこともあります。そのため、シンプルかつ実践しやすいフローを設計し、無駄を省いた運用を心がけることが大切です。
管理する物品は選定する
すべての物品を詳細に管理する必要はなく、管理すべき対象を明確にすることが重要です。例えば、文房具のように頻繁に使用・補充する消耗品は、大まかな把握でも十分な場合があります。一方で、高価な機器や貸出が必要な物品は、厳格な管理が求められます。物品の重要度や金額、使用頻度に応じて、管理対象を適切に選定することで、効率的な運用が可能になります。
物品の管理方法

物品管理には、自社内でシステムを活用して管理する方法と、外部の管理サービスを利用する方法があります。
それぞれの特徴を理解し、自社の状況に適した管理方法を選ぶことが重要です。
管理システム
企業内で物品を適切に管理するために、専用の管理システムを導入する方法があります。システムを活用することで、物品の所在や使用状況をリアルタイムで把握し、紛失や管理ミスを防ぐことができます。
RFID対応タイプ
RFID(無線ICタグ)を活用した物品管理システムは、タグを取り付けた物品を非接触で一括管理できるのが特徴です。バーコードやQRコードと異なり、直接スキャンする必要がないため、大量の物品を迅速に管理できます。倉庫や工場での在庫管理のほか、オフィスの備品管理などに活用されており、物品の持ち出しや返却を自動で記録することが可能です。
QRコード・バーコード対応タイプ
比較的導入しやすい方法として、QRコードやバーコードを活用した管理システムがあります。物品ごとにQRコードやバーコードを付与し、専用のリーダーやスマートフォンアプリでスキャンすることで、情報を管理できます。RFIDに比べると手動でスキャンする手間はありますが、低コストで導入できる点がメリットです。特に、オフィスの備品やIT機器の管理に適しています。
業界・業種特化型タイプ
医療機関や製造業、建設業など、特定の業界向けに開発された管理システムもあります。例えば、医療機関向けのシステムでは、薬品や医療機器の使用履歴や消費期限を管理できる機能が備わっており、安全な運用をサポートします。また、建設業向けでは、現場ごとの資材や工具の管理ができるシステムが提供されています。業界ごとのニーズに特化したシステムを導入することで、より効率的な管理が可能になります。
外部管理サービス
自社内での管理が難しい場合や、より効率的な管理を求める場合は、外部の物品管理サービスを活用する方法もあります。特に、トランクルームのようなサービスを利用することで、保管スペースの削減や管理の手間を軽減することが可能です。
トランクルームを活用することで、企業の倉庫やオフィスにスペースを確保しつつ、物品を安全に保管することができます。長期間使用しない備品や書類などを外部のトランクルームに預けることで、オフィスの整理整頓が進み、業務環境の改善につながります。ただし、必要な物品を取り出す際に手間がかかる場合があるため、頻繁に出し入れが必要な物品管理にはあまり向いていません。
しかし近年は従来のトランクルームよりも利便性が高い「宅配型」の物品管理サービスが登場しています。例えば、「ストックマモル」は、預けた物品をWeb上で確認できるため、どの物品がどこにあるのかをリアルタイムで把握できます。さらに、荷物の受け取りや取り出しの際には、指定した場所まで配送してもらえるため、従業員が直接倉庫へ足を運ぶ必要がありません。
また、不要になった物品は、そのまま廃棄することも可能なため、保管コストの最適化にもつながります。セキュリティ面でも、厳格な社内審査をクリアしたスタッフが荷物を取り扱い、現金輸送車と同等の完全密封車で輸送するため、安全性が確保されています。
このように、外部管理サービスを活用することで、物品の保管だけでなく、管理状況の可視化やセキュリティの強化、業務負担の軽減が一度に実現可能になります。特に、オフィスの省スペース化や管理の効率化を求める企業にとって、非常に有効な手段といえるでしょう。
まとめ

物品管理は、業務の効率化やコスト削減、セキュリティ強化に不可欠です。適切な管理方法を導入することで、無駄を省き、スムーズな運用が可能になります。
管理方法には、RFIDやQRコードなどを活用したシステム導入と、トランクルームなどの外部管理サービスの活用があります。特に、宅配型の管理サービスは、Web上で状況を確認できるだけでなく、必要なときに必要な場所へ配送可能なため、管理の手間を大幅に削減できます。
企業規模や業務形態など自社の状況に応じた最適な管理方法を選び、効率的な物品管理を実現しましょう。