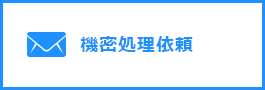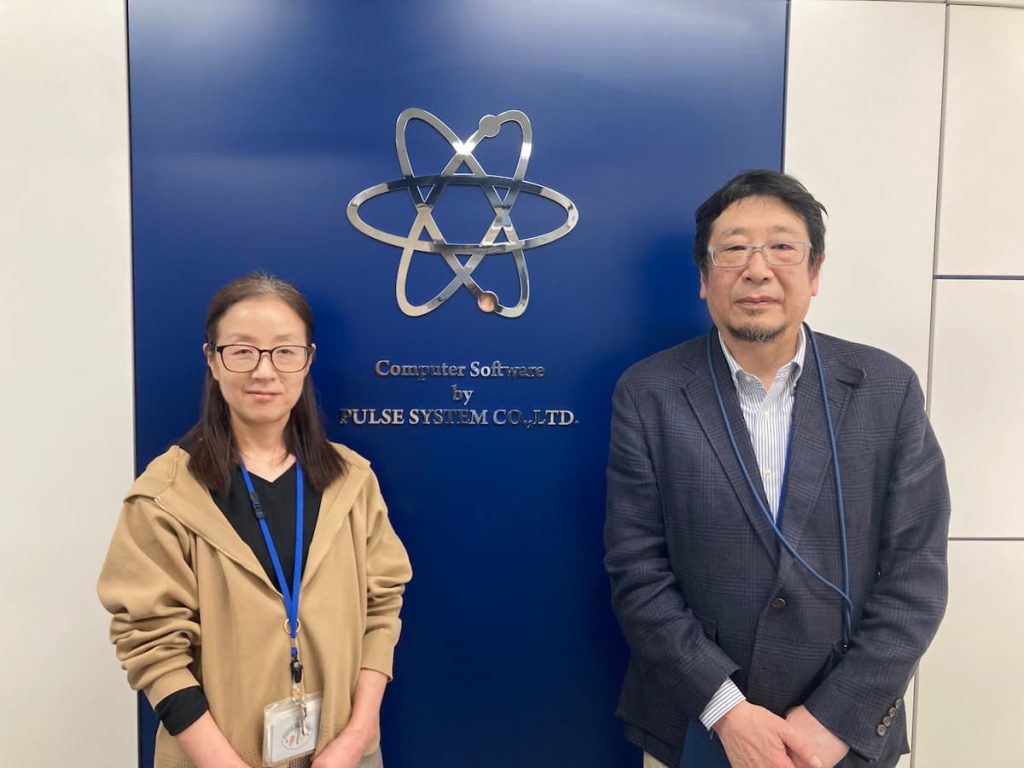
受託型から共創型開発まで、多様な業界の基幹システム開発に携わる独立系SIer
受託型から共創型開発まで、多様な業界の基幹システム開発に携わる独立系システムインテグレーターの株式会社パルス・システム。
2007年から日本パープルの段ボール箱入り機密文書回収サービスをご利用いただいていた同社が、ISMS取得を機にセキュリティ体制のさらなる堅牢化を理由に、オフィス設置の施錠BOX交換型サービス“保護(まもる)くん”へとアップデートすることになった背景や、齎された社内の変化について、総務部の濱谷様と吉川様にお話を伺った。
導入商品・サービス
- 保護(まもる)くん
- 機密抹消
ISMS認証取得時に機密処理方法が課題として指摘。手間のかかるシュレッダーではない方法を探していた
濱谷様:
弊社は、独立系SIer(システムインテグレーター)として多種多様な業界・業種の基幹システム開発に携わっており、オープン系システムソリューション・Web系システムソリューション・クラウドソリューション開発を事業領域として展開しています。
受託型開発に加え、最近増えている共創型開発などさまざまな開発形態に柔軟に対応しながら、少数精鋭の利点を活かしたローコスト、かつ、大規模な開発によって顧客を支援しています。
濱谷様:
弊社が嘗て行っていた情報資産の処分は、シュレッダーに加え、段ボール箱に入れた廃棄書類が5箱程度溜まったところで日本パープルさんへ引き取りをお願いする“保護(まもる)くんスペシャル”との併用で運用していました。
我々の業界では、以前は設計書や仕様書を紙で納品していた関係で、納品時期など特定の期間に廃棄書類が一斉に発生していたのですが、近年は紙の使用率が減っていますので、段ボール箱が一杯になるまでの時間が長くなることによって廃棄予定の機密文書へアクセスすることが容易な状態が長期にわたる事態となりました。
この状態がISMS(ISO27001)認証取得の際に情報資産管理の点で課題となり、セキュリティ委員会から改善を要望されるに至ったのが検討を始めるきっかけとなります。
当初は紙の量も減るのでシュレッダーのみで運用することも考えたのですが、粉砕に時間がかかったり、事業系ごみ処理券のシールを購入して貼る手間や、そもそもゴミとして出しに行くのにも時間がかかったりと、業務を円滑に進めていくうえでは障害にもなるので、以前から知っていたオフィスにポスト型の容器を常設する“保護(まもる)くん”へアップデートすることにより、ISMS取得上の課題を解消することにしました。
書類の処理過程がビデオ撮影されている点も評価
濱谷様:
社内にある廃棄した機密書類へ長期間容易にアクセスできる状態の解消を最も重視していましたので、“保護(まもる)くん”は一度機密書類を入れてしまえば工場で破砕処理をするまでは取り出せない構造ですから、そこは完全にクリアすることができました。
更に、機密書類の入った“保護(まもる)くん”を施錠したまま輸送する運用や、書類を破砕する工程でも人手に触れることが無い点、処理する様子をくまなく監視カメラ等で撮影している点などを導入時に説明していただきましたので、「そこまでしっかりトレーサビリティーが確保できているなら。」ということで契約をさせていただきました。
「保護くんに投入するだけなの?」という嬉しい驚き
吉川様:
導入当初は「本当に“保護(まもる)くん”へ投入するだけなの?」という嬉しさと、驚きがありました。毎回の処分量は10枚20枚といった単位なので、何回かに分けなければ終わらないシュレッダーにかけるよりも楽だという話は社内でしております。
濱谷様:
自由に処分できることが気楽で良いと感じています。導入前は総務部に段ボール箱があり、捨てる量が一気に増えないように総務部のチェックが入っていたのですが、“保護(まもる)くん”の導入によって、社員が気軽に書類を投入できるようになったのもメリットですね。重要書類かどうかわからなければすべて“保護(まもる)くん”へ投入するようにと、我々が社員に促しているくらいです。
吉川様:
そうしたことは弊社ではなかったように思います。もともとシステム開発という特性から従来より厳しいセキュリティ教育は行われておりましたので、社員に高い意識がある前提でコストをかけてでも導入する必要があるという考えは浸透していましたから、“保護(まもる)くん”への移行は極めてスムーズでした。
新たなソフトウェア技術開発者像に向けたスキルアップを通じて、お客様に貢献
濱谷様:
これまでは受託開発が中心で、多くのケースではお客様からのご依頼を受けて業務を開始します。現在はお客様と一緒にシステムをつくることが多くなっています。そのため、お客様のビジョンや業務を理解することが求められており、今までとは違った新しいソフトウェア技術開発者像を描く必要があります。加えて、AI時代においては、AIが作成したプログラムが正しいかどうかを評価することがシステム開発者の役割として加わるでしょう。そのため、我々にとっても勉強の仕方や求める情報が変わるのではないでしょうか。そんなことを意識して、継続的に業務の質を高めて事業を展開してまいります。